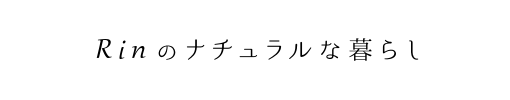こんにちは!Rinです。今から約3年前、「ぬか床」に初挑戦しました。
そして約半年前、「もうどうにもならない!」と思える異臭を放つようになり廃棄し、春に作り直しています。
やってみてわかったことは、維持するための管理やお手入れが難しい!ということです。
そもそも「ぬか床は毎日混ぜる」くらいの知識で始めてしまったら、トラブルの連続でした。美味しくなくなったり、臭くなったり、白カビが生えたり。
トラブルが生じて初めて、必要な管理方法について知ることがとても多かったのです。事前に知っていれば、失敗せずに済んだこともあるかも。
そこで今までの経験から、ぬか床とはどういうものか?必要となる管理方法とお手入れについて、しっかりとまとめたいと思います。
ぬか床とは

ぬか床は、ぬか漬けを漬けるための漬け床のことです。
ぬか漬けを漬けるメリット
ぬか漬けは美味しいということもありますが、野菜をぬか漬けにすると、そのまま野菜を食べるよりもメリットがたくさんあります!
ぬか床は生き物!
ぬか床には目には見えないたくさんの微生物が存在し、増殖と死滅を繰り返しています。
ぬか床は、植物性乳酸菌の乳酸発酵と酵母菌のアルコール発酵により、ぬか漬けが美味しく漬かります。熟成されたぬか床には植物性乳酸菌と酵母菌が、ぬか床1gあたり10億~20億も存在しているのだとか!!!
微生物は生き物なので、管理やお手入れが必要です。
かき混ぜて特定の微生物が異常繁殖するのを防いだり、エサをあげたりしなければいけません。むしろ、微生物を飼っているというか、育てている感覚に近いかも。
ぬか床に必要な管理方法やお手入れ
ぬか床に絶対に必要な管理・お手入れ方法として、次の4つにまとめてみました。
これらのお手入れが必要になる理由は、相互に関係し合っている場合も多いです。
①かき混ぜる

ぬか床を定期的にかき混ぜる目的は、特定の微生物の増殖を防ぐためです。
微生物には、好きな場所があります。産膜酵母は酸素がある上の方に増え、酪酸菌は酸素に触れない容器の底、乳酸菌はその間に住み着くというように。底からしっかりとかき混ぜることにより、増えすぎるのを防ぎます。
白っぽいカビの正体は産膜酵母でありこれらの菌は無害なのですが、増殖すると臭い!ぬか床が臭いとぬか漬けも臭くなるので、美味しくなくなります。
微生物は少なくても発酵が進まなくて困るのですが、増えすぎても困る。ちょうどいいバランスを保つことが重要です。
基本は一日一回混ぜます。でもこれは目安です。
気温の高い時期は微生物の働きが活発になるので、かき混ぜる回数を増やしたり、冷蔵庫に入れるなどします。しばらく混ぜられない場合は、冷蔵庫に入れたり、冷凍もできます。
私は基本的には冷蔵庫に入れていて、4~5日に1回かき混ぜるようにしています。時々は発酵を促すために常温にしたりと、最近は臨機応変にできるようになってきました。

ちなみに、かき混ぜる時は素手の方が常在菌も投入できるのでいいらしいのですが、爪の間にぬかが入るのが嫌なので木べらで混ぜています。
最後ギュッと押して空気を抜く際は素手でしています。手がすべすべになるので、そのときは無駄に手の甲とかでも押しています。
②水分の調整
漬けている野菜から水分が出るので、ぬか床はだんだんゆるくなります。
水分が増えたら、新たに米ぬかを足す(=足しぬか)か、水を捨てます。
捨ててしまうとそこに含まれる微生物や旨味も捨ててしまうことになるし、足しぬかは新たな微生物やエサの供給にもなるので、できれば足しぬかをします。
こんなに米ぬかが必要になるとは知らなかったし、買うとコストが掛かるなと思いました。
③味の調整

味や臭いの変化を感じたら、調整しなければいけません。そのために以下のお手入れが必要です。
かき混ぜる
前述しましたが、特定の微生物が増殖し、酸味が出てきたり変な臭いを防ぐためにかき混ぜます。
塩分の調整
野菜を何度もつけていると、だんだん塩分が薄くなってきます。塩を足してちょうどいい塩分濃度を維持しなければいけません。
個人的には薄味がいいなぁ~なんてかなり薄味にしていたら、ぬか床のトラブル(臭くなる)が起きやすいように感じました!
塩分はぬか漬けにミネラルを与える効果のほかに、悪玉菌・善玉菌を含めた多くの菌の生存を妨げるという役割もあります。
乳酸菌や酵母菌は塩分があっても生きることができ、更に乳酸菌の生成する乳酸も他の微生物の増殖を抑えています。ぬか床は、絶妙なシステムで成り立っていることがわかります。
うま味のもとの投入
うま味のもととして、昆布、にぼし、かつお節などを入れていますが、分解されて無くなるので定期的に入れなければなりません。
ちなみに米ぬかはもちろん、カツオ節、昆布などの持つ栄養素も塩の浸透圧によって野菜に浸透するので、美味しく栄養価の高いぬか漬けとなります。
美味しいぬか漬けが漬かるようになったぬか床は、食べて味を覚えるといいそうです。ぬか床自体は、あまり美味しいものだとは思わないのだけど。
④エサの供給(足しぬかと野菜の出し入れ)

乳酸菌たちは、米ぬかや野菜に含まれる糖分をエサにして、エネルギーに変えて生き続けています。
足しぬかの頻度は1カ月に1回以上、野菜は常に入れておいた方がいいようです。
実はこれを知らなくて、最終的に私はぬか床を廃棄するまでになってしまいました。
頻繁に食べれないからと野菜を入れず、水分も増えないので足しぬかもせず、冷蔵庫に入れて定期的に混ぜるだけしていたら、気づいた時にはくさ~くなっていました。昔の学校とか古い施設のトイレのようなにおいになってしまったのです。
調べてみると、米ぬかも野菜も入れなかったので、エサがなくなり微生物が死滅した状態のようでした。ぬか床は生き物で、エサが必要ということがわからなかったのです。
現在は、とにかく何かしらの野菜を入れるようにしています。
私は家庭菜園をしているのですが、虫食いがあったり捨てようかなと思うような野菜を、積極的に入れています。たくさん漬けても食べきれないので、漬け捨てを今でも行っている感じです。
まとめ

以上、まとめると「ぬか床は生き物!」
育てるには4つの管理(かき混ぜる・水分の調整・味の調整・エサの供給)が必要ということでした。
だいぶ長くなってしまったので、ぬか床の管理は大変なイメージになってしまったかもしれません。
でも初めから仕組みがわかっていれば対処もできるし、慣れるのかなと思います。
今回この記事をまとめるにあたり、改めてぬか漬けが漬かる仕組みの面白さや魅力を感じました。今度こそ、長~く育てたいです♪
参考文献
健康寿命と熟成ぬか床 べんさんのぬかヅケ本舗 [ 石川勉 ]